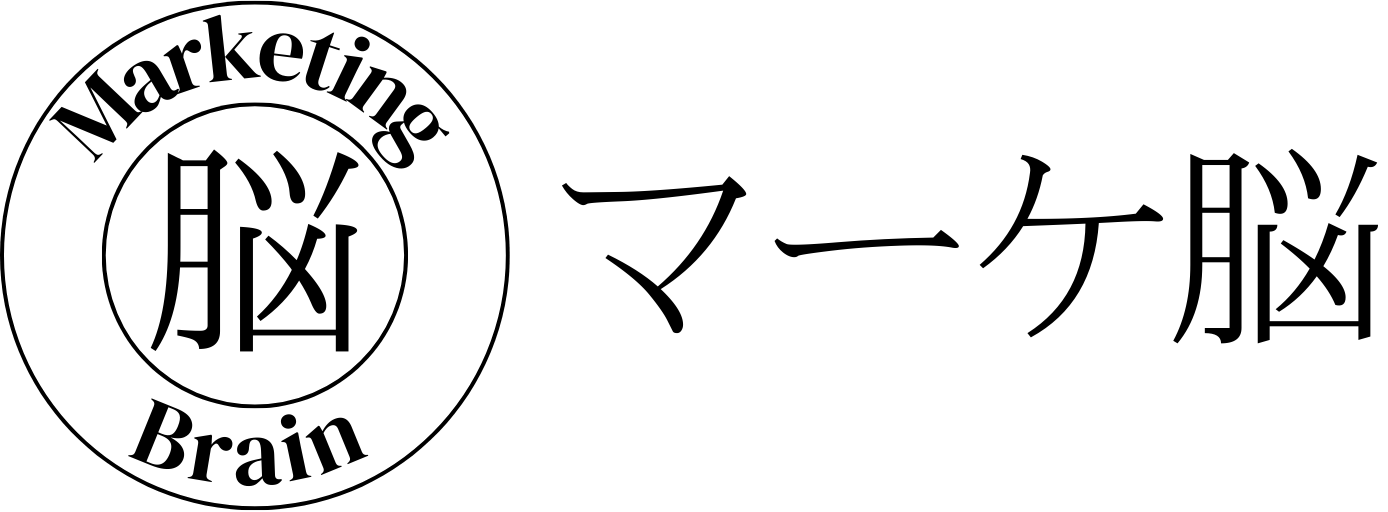「BtoBマーケティングを強化したいが、施策はたくさんあるし、何から手をつければいいか分からない…」
「自社に合った施策はどれなのか、どうやって選べばいいんだろう?」
BtoB企業のマーケティングに携わる人は、必ず一度はこの悩みを抱えます。
Web広告、SEO、展示会、ウェビナー…。世の中には無数のマーケティング施策が存在し、その全体像を把握するだけでも一苦労です。
この記事では、BtoBマーケティングで考えられる施策を102個、網羅的に解説します。さらに、単にリストアップするだけでなく、「なぜその施策が必要なのか」という基本的な考え方から、「自社に合った施策の選び方」、そして具体的な成功事例までを網羅しました。
この記事を最後まで読めば、施策の全体像がクリアになり、明日からあなたの会社が取るべき具体的なアクションプランが見えてくるはずです。
施策の前に!BtoBマーケティングの基本的な考え方

102選のリストを見る前に、少しだけお時間をください。BtoBマーケティングで最も重要な、しかし多くの人が見落としがちな点についてお話しします。
なぜ、いきなり施策から始めてはいけないのか?
「SEOが良いらしいからブログを書こう」「競合がやっているから展示会に出よう」。このように、戦略がないまま流行りの施策に飛びつくと、ほぼ間違いなく失敗します。時間とコストを浪費し、「マーケティングは効果がない」という誤った結論に至ってしまうのです。
成功の鍵は、顧客を理解し、その顧客が購買に至るまでの「心の動き」に寄り添うことです。施策は、そのための「手段」にすぎません。
顧客の購買プロセスを理解する
BtoBにおける顧客の購買行動は、一般的に以下のような心の動きをたどります。
- 認知: 課題を認識し、解決策を探し始める。この段階では、まだあなたの会社のことを知らない。
- 興味・関心: いくつかの解決策を見つけ、情報収集をしながら、それぞれの選択肢への興味を深めていく。
- 比較・検討: 具体的なサービスを数社に絞り込み、機能や価格、実績などを比較し、最も自社に合うものを選ぼうとする。
- 購買・継続: 導入を決定し、実際にサービスを使い始める。そして、その価値を実感しながら継続利用する。
これからご紹介する102の施策は、すべてこの「顧客の心の動き」のいずれかの段階を後押しするために存在します。
ぜひ、「この施策は、どの段階の顧客に、どうアプローチするためのものだろう?」と考えながら読み進めてみてください。そうすることで、単なる知識ではなく、自社で使える「知恵」としてインプットできるはずです。
そもそもBtoBマーケティングとは?(BtoCとの違い)

BtoBマーケティングの施策を理解する上で、その前提となる「BtoB(Business to Business)」取引の特性を知っておくことは非常に重要です。よく比較される「BtoC(Business to Consumer)」との違いを通じて、BtoBマーケティングでなぜ特定の施策が有効なのかを明らかにします。
一言で言えば、BtoBは「企業の課題解決のための、組織的な購買」であるのに対し、BtoCは「個人の欲求を満たすための、個人的な購買」です。この違いが、アプローチのすべてを決定づけます。
| 比較項目 | BtoBマーケティング | BtoCマーケティング |
|---|---|---|
| 顧客 | 企業(組織) | 個人(消費者) |
| 意思決定者 | 複数(担当者、上長、役員など) | 主に個人(または家族) |
| 購買動機 | 合理的・論理的 (企業の課題解決、生産性向上、コスト削減など) | 感情的・感覚的 (好き、欲しい、流行っているなど) |
| 検討期間 | 長い(数ヶ月〜数年) | 短い(数分〜数日) |
| 顧客との関係性 | 長期的・継続的(導入後のサポートが重要) | 短期的・断続的(購入で一旦終了が多い) |
| コミュニケーション | 課題解決に繋がる情報提供、信頼関係の構築 | 認知度向上、ブランドイメージの訴求 |
この表から分かるように、BtoBでは担当者一人の感情では物は売れません。複数の関係者が、それぞれの立場で「本当にこの投資は会社のためになるのか?」を合理的に判断します。
だからこそ、BtoBマーケティングでは、派手な広告よりも、信頼できるデータや導入事例、費用対効果を示すロジカルな情報提供が重要になるのです。
【目的別】BtoBマーケティング施策102選

それでは、お待たせしました。BtoBマーケティングの施策102選を、目的別に解説します。
目的1:まずは知ってもらう、接点をつくる施策
【Webコンテンツ】
1. SEO(検索エンジン最適化)
| 概要 | 自社のWebサイトやブログ記事をGoogleなどの検索結果で上位に表示させ、継続的なアクセスを獲得する施策。 |
| メリット | 一度上位表示されれば広告費をかけずに集客できる。購買意欲の高いユーザーにアプローチしやすい。 |
| デメリット/注意点 | 成果が出るまでに時間がかかる(最低でも半年〜1年)。専門知識が必要。 |
| 向いている企業 | 中長期的な視点でWebからの資産を築きたい企業。 |
| 実践のヒント | まずは自社の顧客が検索しそうな「お悩みキーワード」(例:「人事評価制度 課題」)から対策を始めましょう。 |
SEOのキーワード選定についてはこちらの記事をご覧ください。
2. 課題解決型ブログ
| 概要 | 顧客が抱えるであろう課題や悩みについて、解決策を提示するブログ記事をWebサイト上で公開する。 |
| メリット | 専門家としての信頼性を構築できる。コンテンツが蓄積され、企業の資産になる。 |
| デメリット/注意点 | 継続的な記事制作の体制が必要。直接的な売上にはすぐ繋がらない。 |
| 向いている企業 | 業界の専門知識や独自のノウハウを持っている企業。 |
| 実践のヒント | 顧客からよく受ける質問(FAQ)を一つの記事にまとめることから始めると、ネタに困りません。 |
課題解決型ブログの企画〜運営についてはこちらの記事をご覧ください。
3. 導入事例(記事)
| 概要 | サービスを導入した顧客にインタビューし、導入前の課題や導入後の成果を記事コンテンツにする。 |
| メリット | 第三者の声であるため信頼性が高い。検討段階の顧客の不安を解消し、導入を後押しする。 |
| デメリット/注意点 | 顧客への依頼や取材調整に手間がかかる。成功事例の創出が必要。 |
| 向いている企業 | すべてのBtoB企業。特に、導入効果が数字で示しにくいサービス。 |
| 実践のヒント | 成功した結果だけでなく、「導入で苦労した点とそれをどう乗り越えたか」も正直に書くと、信頼性が増します。 |
導入事例の作成手順についてはこちらの記事をご覧ください。
4. 導入事例(動画)
| 概要 | 顧客へのインタビューを動画で撮影・編集し、WebサイトやSNSで公開する。 |
| メリット | 顧客の表情や声のトーンが伝わり、記事よりもリアルで感情的な共感を生みやすい。 |
| デメリット/注意点 | 撮影・編集にコストと専門スキルが必要。顧客に出演してもらうハードルがやや高い。 |
| 向いている企業 | 顧客の熱量を伝えたい企業。Webサイトや商談でインパクトを与えたい企業。 |
| 実践のヒント | 長い動画だけでなく、SNS用に1分程度の短いハイライト動画も作っておくと活用範囲が広がります。 |
導入事例の作成手順についてはこちらの記事をご覧ください。
5. ホワイトペーパー
| 概要 | 専門的なノウハウや調査データを資料にまとめ、個人情報と引き換えにダウンロードしてもらう。 |
| メリット | 質の高い見込み顧客(リード)の情報を効率的に獲得できる。 |
| デメリット/注意点 | 作成に手間と専門知識がかかる。ダウンロードされても読まれない場合がある。 |
| 向いている企業 | 体系化されたノウハウや独自のデータを持っている企業。 |
| 実践のヒント | 過去のブログ記事やセミナー資料を再編集し、一つの資料にまとめることで効率的に作成できます。 |
ホワイトペーパーの企画〜制作・運用方法についてはこちらの記事をご覧ください。
6. 業界調査レポート
| 概要 | 独自のアンケート調査や市場分析を行い、その結果をレポートとして公開する。 |
| メリット | 業界内での第一人者としての地位を確立できる。メディアに取り上げられる可能性がある。 |
| デメリット/注意点 | 調査の設計や分析に高い専門性が必要。調査費用がかかる場合がある。 |
| 向いている企業 | 業界のトレンドをリードしたい企業。独自のデータで権威性を示したい企業。 |
| 実践のヒント | 調査結果はプレスリリースとして配信しましょう。メディアからの取材に繋がる可能性があります。 |
7. 用語集ページ
| 概要 | 業界の専門用語や、自社サービスに関連するキーワードを解説するページをWebサイトに作る。 |
| メリット | 情報を探し始めたばかりの潜在顧客を、多数集めることができる。SEOに強い。 |
| デメリット/注意点 | 直接的なコンバージョンには繋がりにくい。網羅性を高めるのに手間がかかる。 |
| 向いている企業 | 専門用語が多い業界の企業。Webサイトのアクセス数を増やしたい企業。 |
| 実践のヒント | 各用語の解説ページから、関連するブログ記事やサービスページへ内部リンクを張り巡らせましょう。 |
8. マンガコンテンツ
| 概要 | サービス内容や導入のメリットなどをマンガ形式で表現し、Webサイトや広告で活用する。 |
| メリット | 難しい内容を直感的で分かりやすく伝えられる。SNSなどで拡散されやすい。 |
| デメリット/注意点 | 漫画家の選定や制作ディレクションが必要。制作コストがかかる。 |
| 向いている企業 | サービス内容が複雑で伝わりにくい企業。若手層にアプローチしたい企業。 |
| 実践のヒント | 展示会の配布資料や、営業時のアイスブレイク用資料としても活用できます。 |
9. インフォグラフィック
| 概要 | 調査データや複雑な情報を、図やイラストを用いて一枚の画像にまとめる。 |
| メリット | 視覚的に分かりやすく、SNSでのシェアや他メディアからの引用が期待できる。 |
| デメリット/注意点 | デザインスキルや、情報を整理・要約する能力が必要。 |
| 向いている企業 | 独自のデータや統計情報を持っている企業。 |
| 実践のヒント | ブログ記事の冒頭にインフォグラフィックを配置すると、読者の興味を引きつけ、本文を読んでもらいやすくなります。 |
10. サービス紹介動画
| 概要 | サービスの特長や提供価値を1〜3分程度の短い動画にまとめ、WebサイトのトップページやSNSで公開する。 |
| メリット | テキストの何倍もの情報を短時間で伝えられる。視聴者の記憶に残りやすい。 |
| デメリット/注意点 | 動画制作のコストと時間がかかる。クオリティが低いと逆効果になる。 |
| 向いている企業 | サービスの動きや世界観を視覚的に伝えたい企業。 |
| 実践のヒント | アニメーションを使えば、実写よりも低コストで、複雑な概念を分かりやすく表現できる場合があります。 |
サービス紹介動画の作り方についてはこちらをご覧ください。
11. ノウハウ解説動画
| 概要 | 専門知識やツールの使い方などを、画面キャプチャや講師による解説を交えて動画で説明する。 |
| メリット | 専門性を示し、見込み顧客の教育(ナーチャリング)にも繋がる。 |
| デメリット/注意点 | 定期的な制作・配信体制が必要。 |
| 向いている企業 | 顧客に教えられるノウハウやスキルを持っている企業。 |
| 実践のヒント | YouTubeチャンネルを開設し、動画コンテンツを蓄積していくことで、新たな集客チャネルになります。 |
12. テンプレート配布
| 概要 | 事業計画書やKPI管理シートなど、ターゲット顧客が業務で使える雛形を無料で配布する。 |
| メリット | 非常に実用的なため、質の高いリード情報を獲得しやすい。 |
| デメリット/注意点 | ターゲットの業務を深く理解している必要がある。 |
| 向いている企業 | 顧客の業務改善を支援するツールやコンサルティングを提供している企業。 |
| 実践のヒント | 配布するテンプレートに自社のロゴを入れておくと、利用されるたびにブランド認知が広がります。 |
13. 簡易診断コンテンツ
| 概要 | いくつかの質問に答えることで、自社の課題や成熟度が分かる診断ツールをWebサイトに設置する。 |
| メリット | ゲーム感覚で参加でき、楽しみながら自社の課題に気づかせることができる。 |
| デメリット/注意点 | 診断ロジックの設計や開発にコストがかかる。 |
| 向いている企業 | 顧客の課題が多岐にわたり、言語化が難しいサービスを扱っている企業。 |
| 実践のヒント | 診断結果ページで、それぞれの課題に応じた解決策(自社サービスや記事)を提示しましょう。 |
14. 料金シミュレーター
| 概要 | 利用人数や必要な機能などを入力すると、概算の料金が自動で計算されるツールをWebサイトに設置する。 |
| メリット | 顧客が価格を把握しやすくなり、検討が進む。営業担当者の見積もり作成の手間を削減できる。 |
| デメリット/注意点 | 料金体系が複雑な場合、開発が難しい。 |
| 向いている企業 | 料金体系が明確で、Webサイト上で価格の透明性を示したい企業。 |
| 実践のヒント | シミュレーション結果を保存するためにメールアドレスの入力を求めれば、リード獲得にも繋がります。 |
15. スライド資料の公開
| 概要 | セミナーで使った資料や営業資料などを、SlideShareやSpeaker Deckなどのスライド共有サイトで公開する。 |
| メリット | 既存の資料を再利用できる。サイトからの流入や、資料の埋め込みによる拡散が期待できる。 |
| デメリット/注意点 | 機密情報や非公開情報が含まれていないか、公開前に確認が必要。 |
| 向いている企業 | 定期的にセミナーを開催している企業。質の高い営業資料を持っている企業。 |
| 実践のヒント | 資料の最終ページに、自社サイトへのリンクや問い合わせ先を明記しておきましょう。 |
16. ポッドキャスト配信
| 概要 | 音声番組で、業界ニュースの解説や専門家へのインタビューなどを定期的に配信する。 |
| メリット | 通勤中などの「ながら時間」に聴いてもらえる。リスナーとの親密な関係を築きやすい。 |
| デメリット/注意点 | 継続的な配信が必要。収益化のハードルが高い。 |
| 向いている企業 | 最新情報のキャッチアップが重要な業界の企業。経営者や社員の「人柄」を伝えたい企業。 |
| 実践のヒント | ブログ記事やウェビナーの内容を音声コンテンツとして再利用することで、効率的に配信できます。 |
17. オウンドメディア
| 概要 | 潜在顧客や見込み顧客に役立つ情報を発信し、信頼関係を築きながら将来の受注へと繋げるための自社所有メディア。 |
| メリット | 広告費をかけずに継続的な集客が可能となり、企業の専門性や信頼性を高めることができる。 |
| デメリット/注意点 | 成果が出るまでに時間がかかり、継続的なコンテンツ制作のためのリソースが必要。 |
| 向いている企業 | 顧客の検討期間が長く、専門的な情報提供が購買の決め手となる高価格帯の商材を扱う企業。 |
| 実践のヒント | 誰に何を伝えたいのかを明確にし、読者の課題解決に繋がる質の高いコンテンツを継続的に発信することが成功の鍵です。 |
オウンドメディアの立ち上げ方についてはこちらをご覧ください。
【Web広告】
18. リスティング広告(指名)
| 概要 | 自社の社名やサービス名で検索した、購買意欲が非常に高いユーザーに広告を表示する。 |
| メリット | コンバージョン率が非常に高い。競合に顧客が流れるのを防ぐ。 |
| デメリット/注意点 | 検索ボリュームが少ないため、大きなアクセスは見込めない。 |
| 向いている企業 | すべてのBtoB企業。特に、競合が多い業界の企業。 |
| 実践のヒント | 広告文に「公式サイト」と明記することで、クリック率を高めることができます。 |
19. リスティング広告(一般)
| 概要 | 顧客の課題やニーズに関連するキーワード(例:「営業管理 ツール」)で検索したユーザーに広告を表示する。 |
| メリット | 課題が明確な潜在顧客に直接アプローチできる。短期的に成果が出やすい。 |
| デメリット/注意点 | 人気キーワードはクリック単価が高騰しやすい。継続的に費用がかかる。 |
| 向いている企業 | 短期的にリードを獲得したい企業。WebサイトのSEOがまだ弱い企業。 |
| 実践のヒント | 広告のリンク先を、広告文と関連性の高い専用のランディングページ(LP)に設定することが成功の鍵です。 |
リスティング広告運用の指標と改善方法についてはこちらをご覧ください。
20. ディスプレイ広告
| 概要 | ニュースサイトやブログなどの広告枠に、画像や動画形式の広告(バナー広告)を掲載する。 |
| メリット | まだ課題に気づいていない潜在層に広くアプローチできる。ブランド認知度向上に繋がる。 |
| デメリット/注意点 | リスティング広告に比べてクリック率やコンバージョン率は低い。 |
| 向いている企業 | 新しい市場を創造したい企業。ブランドイメージを浸透させたい企業。 |
| 実践のヒント | ターゲットがよく見るであろう業界専門メディアに絞って配信すると、費用対効果が高まります。 |
21. リターゲティング広告
| 概要 | 一度自社サイトを訪れたユーザーを追いかけ、別のサイトを見ているときに再度広告を表示する。 |
| メリット | 自社に興味があるユーザーに再アプローチできるため、コンバージョン率が高い。 |
| デメリット/注意点 | 配信がしつこいと、ユーザーに不快感を与えるリスクがある。 |
| 向いている企業 | Webサイトにある程度のアクセス数があるすべての企業。 |
| 実践のヒント | 「トップページだけ見た人」「料金ページまで見た人」など、ユーザーの行動に応じて広告内容を変えると効果的です。 |
22. Facebook広告
| 概要 | 企業の役職、業種、興味関心などで詳細にターゲティングし、Facebookのニュースフィード上に広告を配信する。 |
| メリット | BtoBで重要な「役職ターゲティング」の精度が高い。実名制のため信頼性が高い。 |
| デメリット/注意点 | ユーザーは仕事モードではないため、直接的な売り込みは嫌われやすい。 |
| 向いている企業 | 特定の役職者(例:人事部長、マーケティング責任者)にアプローチしたい企業。 |
| 実践のヒント | 広告のリンク先を、売り込み色の薄い「お役立ち資料のダウンロード」や「ウェビナー登録」にすると成功しやすいです。 |
Facebook広告の運用についてはこちらをご覧ください。
23. LinkedIn広告
| 概要 | ビジネス特化SNSであるLinkedIn上で、企業の業種、規模、個人の職種、スキルなどで精緻にターゲティングして広告を出す。 |
| メリット | BtoB広告におけるターゲティング精度が最も高い。決裁権を持つ層にアプローチしやすい。 |
| デメリット/注意点 | 他のSNS広告に比べてクリック単価が高い傾向にある。 |
| 向いている企業 | 高単価な商材を扱っている企業。外資系企業やIT業界をターゲットにする企業。 |
| 実践のヒント | テキスト広告だけでなく、リード獲得用のフォームを広告内に直接設置できる「リードジェネレーションフォーム」が強力です。 |
24. Twitter広告
| 概要 | 特定のキーワードをつぶやいたユーザーや、特定のアカウントをフォローしているユーザーに広告を配信する。 |
| メリット | 情報の拡散力(リツイート)が高い。リアルタイムな話題に乗ってアプローチできる。 |
| デメリット/注意点 | 炎上リスクがある。情報の流れが速く、広告が埋もれやすい。 |
| 向いている企業 | ITエンジニアなど、Twitterを情報収集に活用している層にアプローチしたい企業。 |
| 実践のヒント | イベントの告知やキャンペーンなど、リアルタイム性や拡散性が求められる内容と相性が良いです。 |
25. YouTube広告
| 概要 | ビジネス関連の動画コンテンツの再生前後や再生中に、動画広告(インストリーム広告など)を配信する。 |
| メリット | 動画で多くの情報を伝えられる。特定のチャンネルを指定して、関連性の高いユーザーに配信できる。 |
| デメリット/注意点 | 動画制作のコストがかかる。スキップされやすいため、最初の5秒で惹きつける必要がある。 |
| 向いている企業 | サービスの動きや世界観を視覚的に伝えたい企業。 |
| 実践のヒント | 広告用の短い動画だけでなく、詳しい解説動画を自社のYouTubeチャンネルに用意し、そちらへ誘導するのも有効です。 |
26. 記事広告(タイアップ)
| 概要 | ニュースサイトや業界メディアに費用を払い、第三者の視点から記事形式で自社サービスを紹介してもらう。 |
| メリット | メディアの信頼性を借りることができる。通常の広告よりも自然な形で読んでもらえる。 |
| デメリット/注意点 | 制作費・掲載費が高額になる場合がある。記事内容を完全にコントロールできない。 |
| 向いている企業 | 新しいコンセプトのサービスで、市場の理解を得たい企業。 |
| 実践のヒント | 掲載メディアの編集者と協力し、読者に本当に役立つ情報を提供することを第一に考えると、結果的に成果に繋がります。 |
27. 純広告(バナー広告)
| 概要 | 業界メディアなどのWebサイトの広告枠を期間で買い取り、バナー広告を掲載する。 |
| メリット | 特定の期間、目立つ位置に広告を掲載できるため、ブランド認知度向上に効果的。 |
| デメリット/注意点 | クリック率などの効果測定が難しい場合がある。費用が高額。 |
| 向いている企業 | 業界内での知名度を一気に高めたい企業。イベントの告知など。 |
| 実践のヒント | 広告のリンク先を、汎用的なトップページではなく、広告内容に特化したページにすることが重要です。 |
28. メール広告
| 概要 | ニュースサイトや業界団体などが保有する会員のメールアドレスリストに対し、自社の広告メールを配信してもらう。 |
| メリット | ターゲットとなる業界や職種のリストに、直接メールを届けられる。 |
| デメリット/注意点 | 配信リストの質が成果を大きく左右する。開封されずに削除されることも多い。 |
| 向いている企業 | 特定の業界の多数の企業に、一斉にアプローチしたい企業。 |
| 実践のヒント | 件名が最も重要です。受信者が「自分に関係がある」「読むメリットがある」と感じる件名を考え抜きましょう。 |
29. デジタル音声広告
| 概要 | Spotifyなどの音楽配信サービスや、ポッドキャスト、インターネットラジオの番組中に音声広告を配信する。 |
| メリット | 視覚を使わないため、他の作業中の「ながら聞き」ユーザーにもリーチできる。 |
| デメリット/注意点 | 視覚情報がないため、伝えられる情報が限られる。効果測定が難しい。 |
| 向いている企業 | 広い層にブランド名やサービス名を刷り込みたい企業。 |
| 実践のヒント | 耳に残りやすいサウンドロゴや、「〇〇で検索」といった具体的な行動を促すフレーズを入れると効果的です。 |
【SNS・その他オンライン施策】
30. Facebookページ運用
| 概要 | 企業の公式Facebookページを作成し、製品情報、ブログ更新、イベント告知、社員の様子などを発信する。 |
| メリット | 実名制のため、ビジネス向けの信頼性が高いコミュニケーションが可能。詳細なターゲティングができるFacebook広告との連携がスムーズ。 |
| デメリット/注意点 | オーガニック(無料)でのリーチは年々低下しており、広告活用が前提となりやすい。 |
| 向いている企業 | 顧客やパートナー企業との継続的な関係構築を重視する企業。 |
| 実践のヒント | 一方的な宣伝だけでなく、フォロワーに質問を投げかけたり、コメントに丁寧に返信したりして、コミュニティ作りを意識しましょう。 |
31. Twitterアカウント運用
| 概要 | 140字の短文で、最新情報や業界ニュース、お役立ち情報などをリアルタイムに発信する。 |
| メリット | 情報の拡散力(リツイート)が非常に高い。顧客や業界の「生の声」を収集しやすい。 |
| デメリット/注意点 | 炎上リスクが他のSNSより高い。情報の流れが速く、投稿が埋もれやすい。 |
| 向いている企業 | IT業界など、最新情報のキャッチアップが重要な業界の企業。親しみやすいブランドイメージを構築したい企業。 |
| 実践のヒント | 担当者の「中の人」としての人柄を出すと、親近感が湧きファンが増えやすい傾向にあります。 |
32. LinkedInページ運用
| 概要 | ビジネス特化SNSであるLinkedInに企業ページを作成し、専門性の高いコンテンツや採用情報、企業文化などを発信する。 |
| メリット | ビジネスに関心が高いユーザー層に直接アプローチできる。企業の信頼性や専門性をアピールするのに最適。 |
| デメリット/注意点 | 日本でのユーザー数が他のSNSに比べて少ない。カジュアルなコンテンツには向かない。 |
| 向いている企業 | 外資系企業やグローバルに展開する企業。高単価な専門サービスを扱う企業。 |
| 実践のヒント | 自社の専門家である社員に、個人アカウントで記事を投稿してもらい、それを企業ページでシェアすると信頼性が高まります。 |
33. YouTubeチャンネル運用
| 概要 | 自社の公式YouTubeチャンネルを開設し、導入事例、ノウハウ解説、セミナー動画などを定期的に公開する。 |
| メリット | 動画はテキストよりも多くの情報を伝えられる。コンテンツが資産として蓄積され、Google検索にも表示される。 |
| デメリット/注意点 | 動画の企画、撮影、編集に継続的なリソースが必要。チャンネルが育つまで時間がかかる。 |
| 向いている企業 | 製品の動きや使い方を視覚的に見せたい企業。専門知識を分かりやすく伝えたい企業。 |
| 実践のヒント | 各動画の概要欄に、関連するブログ記事や資料ダウンロードページへのリンクを必ず記載しましょう。 |
34. 社員によるSNS発信
| 概要 | 社員が個人のSNSアカウントで、専門知識や仕事への想い、日々の気づきなどを発信する。 |
| メリット | 企業アカウントよりも人間味があり、信頼されやすい。社員個人のファンが、結果的に企業のファンになる。 |
| デメリット/注意点 | 発信内容のコントロールが難しい。炎上リスクを避けるためのガイドライン策定が必要。 |
| 向いている企業 | 社員の専門性が強みとなる企業(コンサルティング、ITなど)。採用を強化したい企業。 |
| 実践のヒント | 全社で強制するのではなく、発信意欲のある社員を数人選び、成功事例を作ることから始めるのが良いでしょう。 |
35. プレスリリース配信
| 概要 | 新製品、業務提携、調査結果などの企業ニュースを文書にまとめ、メディア向けに配信する。 |
| メリット | メディアに記事として取り上げられれば、無料で大きな認知と社会的信頼を得られる。 |
| デメリット/注意点 | 配信しても必ず記事になるとは限らない。ニュースとしての新規性や社会性が求められる。 |
| 向いている企業 | 定期的に新しいニュースを発信できる企業。業界初や日本初といった話題性のあるサービスを持つ企業。 |
| 実践のヒント | 配信サービス(PR TIMES、@Pressなど)を利用すると、多くのメディア関係者に一度に情報を届けられます。 |
36. 外部メディアへの寄稿
| 概要 | 業界の専門ニュースサイトやビジネス系メディアに、専門家として記事を執筆・提供する。 |
| メリット | メディアの権威性を借りて、自社の専門性と信頼性をアピールできる。質の高い被リンクを獲得でき、SEOにも好影響。 |
| デメリット/注意点 | 執筆に高い専門性と文章力が必要。メディアの編集方針に従う必要がある。 |
| 向いている企業 | 特定分野で高い専門性を持つ社員がいる企業。 |
| 実践のヒント | 記事の最後に執筆者プロフィールとして、自社名とサイトへのリンクを掲載してもらいましょう。 |
37. 比較・一括請求サイト掲載
| 概要 | 複数のサービスを機能や価格で比較できるサイトや、関連資料をまとめて請求できるサイトに自社情報を掲載する。 |
| メリット | 購買意欲が非常に高い、比較検討段階の見込み顧客を獲得できる。 |
| デメリット/注意点 | 掲載料やリード獲得単価が高額になりやすい。価格競争に巻き込まれる可能性がある。 |
| 向いている企業 | 製品の機能や価格に客観的な強みがある企業。 |
| 実践のヒント | 掲載するだけでなく、サイト内の口コミや評価を増やす努力も重要です。導入顧客にレビュー投稿を依頼しましょう。 |
38. チャットボット
| 概要 | Webサイトにチャット形式の自動応答プログラムを設置し、訪問者の質問に24時間365日対応する。 |
| メリット | 訪問者の疑問をその場で解決し、離脱を防ぐ。会話の流れで自然にリード情報を獲得できる。 |
| デメリット/注意点 | シナリオ設計が不十分だと、ユーザーの不満に繋がる。有人チャットへの切り替えも検討が必要。 |
| 向いている企業 | Webサイトへの訪問者数が多く、問い合わせ対応の工数を削減したい企業。 |
| 実践のヒント | 「よくある質問」への回答から始め、徐々に対応範囲を広げていくのがスムーズです。 |
39. ブラウザプッシュ通知
| 概要 | サイト訪問者の許可を得て、Webブラウザを通じて新着記事やセミナーの案内などを直接通知する。 |
| メリット | メールアドレスがなくても、再訪を促すアプローチができる。開封率がメールよりも高い。 |
| デメリット/注意点 | 許可を得るハードルがある。通知が頻繁すぎると、ブロックされやすい。 |
| 向いている企業 | 定期的に新しいコンテンツを公開しているオウンドメディア運営企業。 |
| 実践のヒント | 「新着記事を通知しますか?」だけでなく、「〇〇に関する限定情報をお届けします」など、許可するメリットを具体的に伝えましょう。 |
【オフライン施策】
40. 展示会への出展
| 概要 | 業界のテーマに沿った大規模なイベントに出展し、自社ブースで製品デモや名刺交換を行う。 |
| メリット | 短期間で多くの見込み顧客と直接対話できる。競合の動向や市場のニーズを肌で感じられる。 |
| デメリット/注意点 | 出展料、ブース設営費、人件費などコストが高額。獲得した名刺のフォロー体制が不可欠。 |
| 向いている企業 | 多くのリードと一度に接点を持ちたい企業。製品を直接見せたり、体験してもらったりしたい企業。 |
| 実践のヒント | ブースのデザインやキャッチコピーを工夫し、何をやっている会社なのか一目で分かるようにすることが重要です。 |
41. 自社セミナー開催
| 概要 | 自社で会場を借りるか、オンラインで、特定のテーマに関するセミナー(プライベートセミナー)を開催する。 |
| メリット | 専門性を深くアピールでき、質の高いリードを獲得しやすい。顧客との信頼関係を直接築ける。 |
| デメリット/注意点 | 集客、会場準備、コンテンツ作成に多大な労力がかかる。 |
| 向いている企業 | 独自のノウハウや、語るべきコンテンツを持っている企業。 |
| 実践のヒント | 開催後にアンケートを実施し、満足度や今後の興味関心をヒアリングすることで、次のアプローチに繋げられます。 |
自社セミナーの企画〜運営方法についてはこちらの記事をご覧ください。
42. カンファレンス登壇
| 概要 | 業界の大きなカンファレンスやイベントに、専門家として講演者(スピーカー)として登壇する。 |
| メリット | 業界の第一人者としての権威性を示せる。多くの聴衆に対して一度に影響力を与えられる。 |
| デメリット/注意点 | 登壇者として選ばれるための実績や知名度が必要。プレゼンテーションスキルが求められる。 |
| 向いている企業 | 業界内で知名度のある経営者やエース社員がいる企業。 |
| 実践のヒント | 登壇の様子を録画し、後日Webサイトで公開すれば、二次利用コンテンツとして活用できます。 |
43. イベントスポンサー
| 概要 | 他社が主催するカンファレンスやイベントに、スポンサーとして協賛する。 |
| メリット | イベント自体の集客力を活用して、自社のブランド認知度を高められる。参加者リストを入手できる場合がある。 |
| デメリット/注意点 | スポンサー費用がかかる。費用対効果が見えにくい場合がある。 |
| 向いている企業 | 業界内でのブランディングを強化したい企業。ターゲット層が集まる特定のイベントがある企業。 |
| 実践のヒント | ロゴ掲載だけでなく、休憩時間にCMを流したり、ノベルティを配布したりするなど、参加者の記憶に残る工夫をしましょう。 |
44. オフィス見学ツアー
| 概要 | 実際に社員が働いているオフィスや工場を見学してもらうツアーを企画・開催する。 |
| メリット | 企業の文化や雰囲気を直接感じてもらうことで、透明性を示し、信頼感を醸成できる。 |
| デメリット/注意点 | 受け入れ体制の構築や、セキュリティの確保が必要。 |
| 向いている企業 | 独自の企業文化や、見せるべき生産現場を持つ企業。採用ブランディングを強化したい企業。 |
| 実践のヒント | 見学だけでなく、若手社員との座談会の時間を設けると、参加者の満足度が高まります。 |
45. ミートアップ開催
| 概要 | 特定のテーマ(例:特定の技術、職種)に関心がある人を集め、軽食をとりながらの小規模な交流会を主催する。 |
| メリット | 参加者と密なコミュニケーションが取れる。コミュニティを形成し、将来の採用候補者や顧客と繋がれる。 |
| デメリット/注意点 | 集客や会場運営の手間がかかる。直接的な営業活動はしにくい。 |
| 向いている企業 | エンジニアなど、特定の専門職コミュニティとの関係を築きたい企業。 |
| 実践のヒント | connpassやPeatixといったイベント告知サイトを活用すると、効率的に集客できます。 |
46. 新聞広告
| 概要 | 全国紙や業界紙などの新聞に広告を掲載する。 |
| メリット | 社会的な信頼性が非常に高い。経営層など、年齢層の高いターゲットにリーチしやすい。 |
| デメリット/注意点 | 広告費が高額。効果測定が難しい。 |
| 向いている企業 | 社会的な信用を重視する金融・不動産業界の企業。経営層にアプローチしたい企業。 |
| 実践のヒント | 広告内にQRコードを掲載し、Webサイトの特設ページへ誘導することで、効果測定が可能になります。 |
47. 雑誌広告
| 概要 | ターゲット読者層が明確なビジネス雑誌や業界専門誌に広告を掲載する。 |
| メリット | ターゲットを絞って効率的にアプローチできる。雑誌のブランドイメージを借りることができる。 |
| デメリット/注意点 | 広告費がかかる。Web広告に比べて効果測定がしにくい。 |
| 向いている企業 | 特定の職種(経理、人事など)や業界の担当者にリーチしたい企業。 |
| 実践のヒント | 広告だけでなく、編集タイアップ記事の形で出稿すると、より深くサービスを理解してもらえます。 |
48. 業界専門誌への広告
| 概要 | 特定の業界(建設、医療、農業など)の従事者だけが読むような専門誌に広告を出す。 |
| メリット | 競合が少なく、ニッチなターゲットに確実に情報を届けられる。 |
| デメリット/注意点 | 発行部数が少なく、リーチできる人数は限られる。 |
| 向いている企業 | 特定の業界に特化した専門的な製品・サービスを扱っている企業。 |
| 実践のヒント | 広告だけでなく、その業界の課題を解決するような内容の連載記事を寄稿するのも有効です。 |
49. 交通広告
| 概要 | 駅構内、電車内、バス、タクシーなどにポスターや動画の広告を掲載する。 |
| メリット | 特定のエリアで働くビジネスパーソンに、毎日繰り返し訴求できる(反復効果)。 |
| デメリット/注意点 | 費用が高額。詳細なターゲティングは難しい。 |
| 向いている企業 | ビジネス街(丸の内、大手町など)で働く層をターゲットにするSaaS企業など。 |
| 実践のヒント | 電車内広告では、移動中の短い時間で理解できるよう、シンプルで分かりやすいメッセージが求められます。 |
50. タクシー広告
| 概要 | タクシーの後部座席に設置されたディスプレイで、動画広告を配信する。 |
| メリット | 経営者層や管理職など、ビジネスのキーパーソンの利用率が高い。個室空間で広告に集中してもらいやすい。 |
| デメリット/注意点 | 費用が高額。しつこいと感じられるリスクもある。 |
| 向いている企業 | 決裁権を持つ層に直接アプローチしたい高単価商材の企業。 |
| 実践のヒント | 「経営者の皆様へ」といったように、ターゲットに直接語りかけるメッセージが有効です。 |
51. ラジオCM
| 概要 | 特定のラジオ番組のスポンサーとなり、番組中にCMを流す。 |
| メリット | 車で移動中の営業担当者や、特定の趣味を持つ経営者など、ニッチな層にリーチできる。 |
| デメリット/注意点 | 音声しかなく、伝えられる情報が限られる。効果測定が非常に難しい。 |
| 向いている企業 | 運送業や営業担当者など、特定の職種をターゲットにする企業。 |
| 実践のヒント | 耳に残りやすいサウンドロゴや、覚えやすいサービス名を連呼することが重要です。 |
52. テレビCM
| 概要 | テレビ番組の間にCMを放映し、広範囲に一気に認知度を高める。 |
| メリット | 最もリーチが広く、絶大なブランド認知と社会的信頼性を獲得できる。 |
| デメリット/注意点 | 制作費・放映費が極めて高額。BtoBでは費用対効果を合わせるのが非常に難しい。 |
| 向いている企業 | 業界のガリバー企業や、上場を機に一気に知名度を上げたい企業。 |
| 実践のヒント | 最近では、特定の地域や時間帯に絞って放映できる安価なプランも出てきています。 |
53. 書籍の出版
| 概要 | 自社のノウハウ、創業ストーリー、経営者の思想などを一冊の本として商業出版する。 |
| メリット | 企業の権威性とブランド価値を飛躍的に高める。「〇〇の著者」という最強の肩書きが手に入る。 |
| デメリット/注意点 | 出版までに多大な時間と労力がかかる。商業出版のハードルは高い。 |
| 向いている企業 | 業界の第一人者を目指す企業。独自のメソッドを体系化している企業。 |
| 実践のヒント | まずは出版社に企画を持ち込むことから始まります。ブログなどで情報発信し、実績を作っておくと有利です。 |
54. DM(ダイレクトメール)
| 概要 | ターゲット企業の担当者宛に、パンフレットや手紙、ノベルティなどを直接郵送する。 |
| メリット | メールが溢れる中で物理的に届くため、開封率が高く印象に残りやすい。 |
| デメリット/注意点 | 印刷・郵送コストがかかる。送付リストの精度が成果を左右する。 |
| 向いている企業 | ITリテラシーが高くない業界や、決裁権を持つ年配の層にアプローチしたい企業。 |
| 実践のヒント | 立体的なDMや、思わず開封したくなるような変わった形の封筒を使うと、効果が高まります。 |
55. CxOレター
| 概要 | 社長や役員などの経営層(CxO)宛に、経営課題に踏み込んだ内容の手紙を送付する。 |
| メリット | 担当者レベルでは難しい、トップダウンでのアプローチが可能になる。 |
| デメリット/注意点 | 相手企業のビジネスを深く理解し、質の高い提案を書く必要がある。本人に届くとは限らない。 |
| 向いている企業 | 企業の経営根幹に関わるような高額なコンサルティングやシステムを扱う企業。 |
| 実践のヒント | 差出人を自社の社長名にし、手書きの署名を加えるなど、特別感を演出することが重要です。 |
56. ノベルティグッズ配布
| 概要 | 社名やロゴの入ったボールペン、カレンダー、付箋などの実用的なグッズを作成し、展示会や商談で配布する。 |
| メリット | 日常業務で使ってもらうことで、継続的に自社ブランドを思い出してもらえる。 |
| デメリット/注意点 | ありきたりな物だと捨てられてしまう。質の高いグッズはコストがかかる。 |
| 向いている企業 | 顧客との接触機会が多い企業。ブランドの親しみやすさを向上させたい企業。 |
| 実践のヒント | ターゲットが本当に使うであろう、少し気の利いたアイテム(PCスタンド、高品質なノートなど)を選ぶと喜ばれます。 |
57. FAX DM
| 概要 | 企業のFAX番号リストに対して、キャンペーンやセミナーの案内を一斉に送付する。 |
| メリット | 低コストで多くの企業に一斉に情報を届けられる。Webを見ない層にもリーチできる。 |
| デメリット/注意点 | クレームに繋がりやすく、企業のイメージを損なうリスクがある。多くの企業でFAXが使われなくなっている。 |
| 向いている企業 | 中小企業や、FAX文化が根強く残る業界(建設、不動産、医療、介護など)をターゲットにする企業。 |
| 実践のヒント | 送付する時間帯(始業直後など)や、送付先の業種を慎重に選び、クレーム時の連絡先を明記することが必須です。 |
58. テレアポ
| 概要 | 企業リストに基づき、まだ接点のない企業に電話をかけ、製品紹介や商談のアポイント獲得を目指す。 |
| メリット | ターゲットに直接アプローチでき、すぐに反応がわかる。市場のニーズを直接ヒアリングできる。 |
| デメリット/注意点 | 成功率が低く、精神的な負担が大きい。相手に悪い印象を与えるリスクがある。 |
| 向いている企業 | ターゲットリストが明確で、単価の高い商材を扱っている企業。 |
| 実践のヒント | いきなり売り込むのではなく、「〇〇に関する情報提供ですが」と切り出すと、話を聞いてもらいやすくなります。 |
59. パートナー企業からの紹介
| 概要 | 協業している企業や、関連サービスを提供している企業(アライアンスパートナー)から、見込み顧客を紹介してもらう。 |
| メリット | 紹介者のお墨付きがあるため、信頼度が高く、受注に繋がりやすい。 |
| デメリット/注意点 | パートナー企業との良好な関係構築が不可欠。紹介が生まれる仕組み作りが必要。 |
| 向いている企業 | 自社サービスと親和性の高いサービスを提供している他社と繋がりがある企業。 |
| 実践のヒント | 紹介してくれたパートナーにインセンティブ(紹介料)を支払う制度を設けると、協力が得やすくなります。 |
目的2:興味を深め、信頼を育てる施策
60. MA(マーケティングオートメーション)導入
| 概要 | メール配信、顧客行動の追跡、スコアリングなどを自動化し、効率的に見込み顧客を育成するツールを導入・活用する。 |
| メリット | 膨大な数の見込み顧客に対し、個々の興味に合わせたアプローチを自動で行える。マーケティング活動の成果を可視化できる。 |
| デメリット/注意点 | 導入・運用コストがかかる。ツールを使いこなすには、戦略設計やコンテンツが不可欠。 |
| 向いている企業 | 獲得したリードをフォローしきれていない企業。リード数が1000件を超えている企業。 |
| 実践のヒント | まずは「資料請求者へのお礼メールと3日後のフォローメールを自動化する」など、簡単なシナリオから始めてみましょう。 |
61. メルマガ定期配信
| 概要 | ブログの更新情報、業界ニュース、セミナー案内などを、定期的(週1回など)にメールで配信する。 |
| メリット | 低コストで継続的に顧客と接点を持ち、自社を忘れられないようにする(リマインド効果)。 |
| デメリット/注意点 | 内容が面白くないと、開封されなくなったり、配信停止されたりする。 |
| 向いている企業 | 定期的に発信する情報があるすべての企業。 |
| 実践のヒント | 毎回宣伝ばかりではなく、読者の役に立つ情報を8割、宣伝を2割くらいのバランスにすると、長く読んでもらえます。 |
62. ステップメール配信
| 概要 | 資料請求やセミナー申込といった特定のアクションを起点に、あらかじめ用意した複数のメールを、決められたスケジュール(3日後、7日後など)で自動配信する。 |
| メリット | 顧客の興味の熱が高いうちに、段階的に情報を提供し、スムーズに次の行動へ誘導できる。 |
| デメリット/注意点 | 効果的なシナリオ(配信内容とタイミング)の設計にノウハウが必要。 |
| 向いている企業 | 顧客の検討プロセスがある程度決まっているサービスを扱う企業。 |
| 実践のヒント | 「サービスの理解を深める→導入事例で共感を得る→個別相談会へ誘導する」といったストーリーでシナリオを設計します。 |
63. 休眠顧客の掘り起こし
| 概要 | 過去に接点があったものの、長期間反応のない顧客リスト(休眠顧客)に対し、特別なキャンペーンや最新の導入事例などで再度アプローチする。 |
| メリット | 新規リード獲得よりも低コストで、商談機会を創出できる可能性がある。 |
| デメリット/注意点 | 下手なアプローチは配信停止やクレームに繋がる。 |
| 向いている企業 | 過去に獲得したリードが大量に眠っている企業。 |
| 実践のヒント | 「〇〇様、お久しぶりです」といった件名や、過去のやり取りを踏まえたパーソナルな内容にすると、反応率が上がります。 |
64. セグメント配信
| 概要 | 顧客リストを役職、業種、興味関心、過去の行動などに基づいてグループ分け(セグメント化)し、それぞれのグループに最適な内容のメールを配信する。 |
| メリット | 全員に同じメールを送るよりも、自分事として捉えてもらいやすく、開封率やクリック率が高まる。 |
| デメリット/注意点 | セグメント分けの作業や、複数のメールを作成する手間がかかる。 |
| 向いている企業 | 顧客層が多様で、それぞれニーズが異なる企業。 |
| 実践のヒント | まずは「人事担当者向け」「営業責任者向け」など、分かりやすい職種別のセグメントから始めてみましょう。 |
65. インサイドセールス
| 概要 | 電話やメール、Web会議ツールなどを活用し、社内から非対面で見込み顧客の育成や選別を行う営業手法。 |
| メリット | 訪問営業よりも効率的に多くの顧客にアプローチできる。マーケティングと営業の橋渡し役となり、商談の質を高める。 |
| デメリット/注意点 | 組織の立ち上げや人材育成にコストがかかる。対面でない分、高度なコミュニケーションスキルが求められる。 |
| 向いている企業 | 多くのリードを抱えているが、営業が対応しきれていない企業。高単価な商材を扱う企業。 |
| 実践のヒント | MAと連携し、スコアの高いリードから優先的にアプローチする体制を築くと、非常に効果的です。 |
66. 育成目的のウェビナー
| 概要 | 新規リード獲得目的ではなく、既存の見込み顧客向けに、より専門的な内容や製品の応用的な使い方をテーマにしたウェビナーを開催する。 |
| メリット | 顧客の製品理解度を高め、購買意欲を醸成できる。顧客の疑問や悩みを直接ヒアリングできる。 |
| デメリット/注意点 | 集客対象が限られるため、大規模な開催は難しい。 |
| 向いている企業 | 製品の機能が豊富な企業。顧客の活用レベルに差がある企業。 |
| 実践のヒント | 参加者限定で、講師に直接質問できるQ&Aの時間を長めに設けると、満足度が高まります。 |
67. クローズドな勉強会
| 概要 | 特定の条件(例:特定の資料をダウンロードした人)を満たした見込み顧客だけを招待し、少人数での勉強会やディスカッションを行う。 |
| メリット | 参加者との距離が近く、深い信頼関係を築きやすい。参加者同士の交流が新たな価値を生むこともある。 |
| デメリット/注意点 | 企画・運営に手間がかかる。集客が難しい場合がある。 |
| 向いている企業 | 高単価なコンサルティングサービスなど、信頼関係が特に重要な商材を扱う企業。 |
| 実践のヒント | 会の最後に、希望者向けに個別相談の時間を設けておくと、スムーズに商談に繋げられます。 |
68. 限定コンテンツの提供
| 概要 | メルマガ読者や、特定のセミナー参加者など、限られた人にしか見られない特別なコンテンツ(記事、動画、レポートなど)を提供する。 |
| メリット | 「自分は特別扱いされている」という感覚を与え、顧客ロイヤリティを高める。メルマガなどの登録を促すフックになる。 |
| デメリット/注意点 | コンテンツの作成に手間がかかる。限定感を出しすぎると、見られない人の不満に繋がる可能性もある。 |
| 向いている企業 | 質の高いコンテンツを継続的に制作できる企業。 |
| 実践のヒント | 「〇〇セミナー参加者限定公開」として、セミナーの録画動画や資料を配布するのが最も手軽な方法です。 |
69. 育成目的のリターゲティング広告
| 概要 | 一度サイトを訪れた見込み顧客に対し、「導入事例」や「お客様の声」、「よくある質問への回答」といった、検討を後押しする内容の広告を表示する。 |
| メリット | 顧客の検討段階に合わせて、適切なタイミングで不安や疑問を解消する情報を提供できる。 |
| デメリット/注意点 | 広告クリエイティブを複数パターン用意する必要がある。 |
| 向いている企業 | 顧客の検討期間が長く、その間に忘れられがちなサービスを扱う企業。 |
| 実践のヒント | 「料金ページを見た人には、導入事例広告を見せる」といったように、顧客のサイト内行動と連動させると効果的です。 |
70. リードスコアリング
| 概要 | 見込み顧客の属性(役職、業種など)や行動(メール開封、サイト訪問など)を点数化し、購買意欲の高さ(確度)を可視化する。 |
| メリット | 営業担当者が、確度の高いリードから優先的にアプローチできるようになり、営業効率が劇的に向上する。 |
| デメリット/注意点 | 適切な点数設定に試行錯誤が必要。MAツールなどの導入が前提となる。 |
| 向いている企業 | リード数が多く、どの顧客からアプローチすべきか分からなくなっている企業。 |
| 実践のヒント | 最初は「料金ページの閲覧:10点」「役職が部長以上:15点」などシンプルなルールから始め、徐々に精緻化していきましょう。 |
71. 個別相談会の案内
| 概要 | メルマガやウェビナーの参加者など、ある程度興味が深まっている見込み顧客に対し、専門家が1対1で相談に乗る機会を案内する。 |
| メリット | 顧客一人ひとりの具体的な課題に寄り添った提案ができ、高い確率で商談に繋がる。 |
| デメリット/注意点 | 対応する専門家のリソースを確保する必要がある。 |
| 向いている企業 | 顧客の課題が個別性が高く、パッケージ化された提案が難しいサービスを扱う企業。 |
| 実践のヒント | Webサイトからいつでも予約できるカレンダーツール(Calendlyなど)を導入すると、日程調整の手間が省けます。 |
72. 顧客向けニュースレター
| 概要 | 紙媒体の会報誌や、デザイン性の高いHTMLメールなどで、読み物としての価値が高いニュースレターを送付する。 |
| メリット | デジタルの情報が溢れる中で、物理的に届く紙媒体や、デザイン性の高いメールは特別感を演出し、記憶に残りやすい。 |
| デメリット/注意点 | 印刷・郵送コストや、デザイン・編集の工数がかかる。 |
| 向いている企業 | ブランディングを重視する企業。高単価な商材を扱う企業。 |
| 実践のヒント | 業界の著名人へのインタビュー記事や、読み応えのあるコラムなどを掲載すると、価値が高まります。 |
73. パーソナライズドメール
| 概要 | システムからの一斉配信ではなく、営業担当者が個人名で、顧客一人ひとりの状況に合わせてカスタマイズしたメールを送る。 |
| メリット | 一斉配信メールよりも圧倒的に開封・返信率が高い。人間的な関係を構築できる。 |
| デメリット/注意点 | 一通一通作成するのに時間がかかる。 |
| 向いている企業 | 顧客単価が高く、一社一社との関係構築が重要な企業。 |
| 実践のヒント | 顧客の過去の問い合わせ内容や、Webサイトでの行動履歴を踏まえた内容にすると、「自分のことを理解してくれている」と感じてもらえます。 |
74. 導入事例の定期共有
| 概要 | 新しい導入事例が作成されるたびに、その内容をメルマガや個別のメールで見込み顧客に共有する。 |
| メリット | 「自分の業界と同じだ」「この課題はうちと一緒だ」といった共感を生み、検討を再開させるきっかけになる。 |
| デメリット/注意点 | 導入事例を継続的に作成する体制が必要。 |
| 向いている企業 | 顧客の業種や規模が多岐にわたる企業。 |
| 実践のヒント | メールを送る際に、「〇〇業界の事例にご興味はありますか?」といった形で、相手の状況に合わせた事例を送ると効果的です。 |
75. 顧客の行動履歴に基づくアプローチ
| 概要 | MAツールなどを活用し、特定のページ(料金、導入事例など)を何度も見ている顧客を特定し、インサイドセールスなどからアプローチする。 |
| メリット | 顧客がまさに興味を持っているタイミングで、的確な情報を提供できるため、商談に繋がりやすい。 |
| デメリット/注意点 | 行動を監視されていると受け取られないよう、自然なアプローチが求められる。 |
| 向いている企業 | MAツールを導入しており、インサイドセールスとの連携が取れる企業。 |
| 実践のヒント | 「〇〇のページをご覧いただいているようですが、何かご不明な点はございませんか?」といった、手助けを申し出るスタンスのアプローチが有効です。 |
目的3:比較・検討を後押しし、選ばれるための施策
76. サービス資料
| 概要 | 見込み顧客が営業担当者の介在なしに自力でサービスの価値を理解し、検討度合いを高めるための網羅的な説明資料です。 |
| メリット | 24時間365日働く営業パーソンのように見込み顧客を育成し、効率的に質の高い商談機会を創出できます。 |
| デメリット/注意点 | 作成にリソースがかかる上、情報を詰め込みすぎたり、売り手目線の内容になったりすると、顧客に読まれず効果が出ない点に注意が必要です。 |
| 向いている企業 | Webサイトからのリード獲得や、営業の効率化を目指したいBtoB企業全般、特に無形商材や高関与商材を扱う企業に向いています。 |
| 実践のヒント | まずは無料テンプレートを活用して構成の型を掴み、機能の羅列ではなく「顧客の課題をどう解決できるか」という買い手目線で内容を記述することが成功の鍵です。 |
サービス資料の作り方や使えるテンプレートについてはこちらをご覧ください。
77. SFA(営業支援ツール)導入
| 概要 | 商談の進捗状況、顧客とのやり取り、タスクなどを一元管理し、営業活動全体を効率化・可視化するツールを導入する。 |
| メリット | 営業担当者間の情報共有がスムーズになり、属人化を防ぐ。マネージャーが全体の状況を把握し、的確な指示を出せるようになる。 |
| デメリット/注意点 | 導入コストがかかる。営業担当者が入力の手間を面倒に感じ、定着しないことがある。 |
| 向いている企業 | 営業担当者が複数名おり、情報共有や案件管理に課題を感じている企業。 |
| 実践のヒント | 「SFAに入力すれば、報告書を書かなくて済む」など、現場の営業担当者にとってのメリットを明確に伝えることが定着の鍵です。 |
78. CRM(顧客関係管理)導入
| 概要 | マーケティング、営業、カスタマーサポートなど、部署を横断して顧客情報を一元管理し、全社で最適なアプローチを行うためのシステム。 |
| メリット | 顧客の過去のやり取りをすべて把握した上で対応できるため、顧客体験が向上する。 |
| デメリット/注意点 | SFAよりも大規模なシステムとなり、導入・定着の難易度が高い。 |
| 向いている企業 | 顧客との長期的な関係構築を重視し、全社で顧客中心の体制を築きたい企業。 |
| 実践のヒント | CRMは単なるツールではなく、「顧客中心」という思想そのものです。導入前に、経営層がその重要性を全社に発信することが不可欠です。 |
79. オンライン商談ツール活用
| 概要 | ZoomやGoogle Meetなどのツールを活用し、遠隔地の顧客とも画面共有しながら顔を見て商談を行う。 |
| メリット | 移動時間がなくなり、営業担当者が1日に対応できる商談数が増える。全国・全世界の顧客にアプローチできる。 |
| デメリット/注意点 | 対面に比べて、相手の雰囲気や細かいニュアンスが伝わりにくい場合がある。通信環境に左右される。 |
| 向いている企業 | 広範囲のエリアをターゲットにしている企業。営業の効率化を目指す全ての企業。 |
| 実践のヒント | 背景を自社のロゴが入ったバーチャル背景にしたり、商談相手に合わせて画面に映る資料を最適化したりする工夫が有効です。 |
80. 無料トライアル提供
| 概要 | 期間や機能を限定して、製品・サービスを無料で試してもらう機会を提供する。 |
| メリット | 顧客が実際にサービスに触れることで、価値を実感し、導入後のイメージを具体的に持てる。 |
| デメリット/注意点 | トライアル期間中にフォローしないと、使われないまま終わってしまう。サポート体制が必要。 |
| 向いている企業 | SaaSなど、実際に使ってもらうことで良さが伝わるサービスを提供している企業。 |
| 実践のヒント | トライアル開始時に、使い方の簡単なガイドを送ったり、目標設定のサポートをしたりすると、トライアルの成功率が高まります。 |
81. 製品デモの実施
| 概要 | 商談中に、実際の製品の操作画面を見せながら、顧客の課題に合わせた具体的な使い方や機能を分かりやすく説明する。 |
| メリット | 顧客が「自分たちが使うとどうなるか」をリアルに想像できる。質疑応答を通じて、その場で疑問を解消できる。 |
| デメリット/注意点 | 顧客の課題を事前にヒアリングし、それに合わせたデモシナリオを準備する必要がある。 |
| 向いている企業 | 機能が豊富なソフトウェアや、操作性が強みのサービスを扱う企業。 |
| 実践のヒント | すべての機能を見せるのではなく、顧客の課題解決に直結する機能に絞って見せることが重要です。 |
82. 競合比較表の作成
| 概要 | 競合サービスと自社サービスを、機能、価格、サポート体制などの観点で客観的に比較した資料を作成し、商談で活用する。 |
| メリット | 顧客が比較検討する手間を省ける。自社の優位性をロジカルに伝えられる。 |
| デメリット/注意点 | 競合の情報を正確に把握する必要がある。自社に都合の良い情報ばかりだと、信頼性を失う。 |
| 向いている企業 | 競合が多く、顧客がどのサービスを選べば良いか迷いがちな市場にいる企業。 |
| 実践のヒント | 機能の有無(〇✕)だけでなく、「なぜこの機能がないのか(思想の違いなど)」まで説明できると、より説得力が増します。 |
83. 提案資料のフォーマット化
| 概要 | 誰が作っても一定以上の品質が保てるよう、提案書の構成やデザインの雛形(テンプレート)を用意しておく。 |
| メリット | 営業担当者が資料作成にかける時間を短縮できる。企業として統一感のある、質の高い提案が可能になる。 |
| デメリット/注意点 | フォーマットに頼りすぎると、顧客に合わせたカスタマイズがおろそかになる危険性がある。 |
| 向いている企業 | 営業担当者が複数名おり、提案の質にばらつきがある企業。 |
| 実践のヒント | 会社の基本情報や導入実績など、共通で使える部分は固定にし、顧客の課題や提案内容は個別に書き込む形式がおすすめです。 |
84. 受注顧客の傾向分析
| 概要 | SFAやCRMに蓄積されたデータを用いて、どのような業種、規模、課題を持つ顧客が契約に至りやすいかを分析する。 |
| メリット | 営業活動の「勝ちパターン」が見つかる。確度の高い見込み顧客にリソースを集中できるようになる。 |
| デメリット/注意点 | 分析するためには、データが正しく蓄積されていることが前提となる。 |
| 向いている企業 | ある程度の受注実績データが蓄積されている企業。 |
| 実践のヒント | 受注顧客だけでなく、失注顧客のデータも合わせて分析することで、より多くの示唆が得られます。 |
85. 失注要因の分析
| 概要 | なぜ商談が契約に至らなかったのかを、価格、機能、タイミング、競合などの観点から分析し、記録する。 |
| メリット | サービスや価格設定、営業プロセスの具体的な改善点が見つかる。 |
| デメリット/注意点 | 顧客から本当の失注理由を聞き出すのは難しい場合がある。 |
| 向いている企業 | 受注率の伸び悩みに課題を感じている企業。 |
| 実践のヒント | 失注した際に、営業担当者が必ずSFAに理由を入力するルールを徹底することが第一歩です。 |
86. 営業ロープレの定期開催
| 概要 | 営業担当者同士で、顧客役と営業役に分かれて模擬商談(ロールプレイング)を定期的に行い、提案スキルを磨く。 |
| メリット | 新人営業の早期育成に繋がる。他の担当者の良い点や改善点を客観的に学ぶことができる。 |
| デメリット/注意点 | マンネリ化しないよう、毎回テーマや設定を変える工夫が必要。 |
| 向いている企業 | 営業組織全体の提案力を底上げしたい企業。 |
| 実践のヒント | ロープレの様子を録画し、後で全員でフィードバックし合うと、学びが深まります。 |
87. 迅速な見積もり提出
| 概要 | 顧客から依頼された見積もりを、可能な限りスピーディーに提出できる社内体制やツールを整備する。 |
| メリット | 対応の速さが、顧客からの信頼感に繋がる。競合他社よりも早く検討の土台に乗ることができる。 |
| デメリット/注意点 | スピードを重視するあまり、内容にミスがあってはならない。 |
| 向いている企業 | 見積もり依頼が多い企業。営業担当者が見積もり作成に時間を取られている企業。 |
| 実践のヒント | 見積もり作成ツールや、SFAの見積もり機能などを活用すると、ミスなく迅速に作成できます。 |
88. 決裁者へのアプローチ
| 概要 | 商談の担当者だけでなく、最終的な意思決定者(決裁者)は誰かを見極め、その人に響くための資料やアプローチを準備する。 |
| メリット | 担当者レベルで話が進んでも、最後の最後で覆される「ちゃぶ台返し」を防ぐ。 |
| デメリット/注意点 | 担当者を飛び越えて決裁者にアプローチすると、担当者の心証を損ねるリスクがある。 |
| 向いている企業 | 導入の意思決定に複数の部署や役職が関わる、エンタープライズ向けのサービスを扱う企業。 |
| 実践のヒント | 担当者に「〇〇様の上長様は、どのような点を重視されますか?」とヒアリングし、味方につけながら進めるのが王道です。 |
目的4:長く使い続けてもらい、ファンになってもらう施策
89. カスタマーサクセス部門の設立
| 概要 | 顧客の成功を能動的に支援する専門チームを作り、解約防止を目指す。 |
| メリット | LTV(顧客生涯価値)を最大化できる。ポジティブな顧客体験は、良い口コミや紹介に繋がる。 |
| デメリット/注意点 | 専門のスタッフとリソースが必要。すぐに売上に繋がる短期的な投資ではない。 |
| 向いている企業 | サブスクリプションモデル(SaaSなど)で、継続的な顧客関係が重要なビジネス。 |
| 実践のヒント | まずは新規顧客が共通でつまずく点を分析し、それを未然に防ぐための「オンボーディング」プログラムを構築することから始めましょう。 |
90. オンボーディングプログラム
| 概要 | 新規顧客がスムーズに利用を開始し、基本的な機能を学び、サービスで最初の「成功体験」を得るまでを支援する体系的なプロセス。 |
| メリット | サービスの定着率を高め、早期の解約を防ぐ。サポートデスクへの問い合わせを削減する。 |
| デメリット/注意点 | マニュアルやチュートリアル動画の作成、場合によっては専任担当者が必要。 |
| 向いている企業 | ある程度機能が複雑なサービスや、多機能なサービス。 |
| 実践のヒント | 自動化されたウェルカムメール、チュートリアル動画、1対1のウェルカムコールなどを組み合わせ、包括的な体験を提供しましょう。 |
91. 定期的なフォローアップ
| 概要 | 電話やメールで定期的に顧客に連絡を取り、利用状況や困っていることがないかを確認する。 |
| メリット | 顧客が大切にされていると感じる。問題が大きくなる前に、潜在的な課題を特定し解決できる。 |
| デメリット/注意点 | 頻繁すぎたり、価値のない連絡だったりすると、迷惑がられる可能性がある。フォローのスケジュール管理が必要。 |
| 向いている企業 | 顧客単価の高い企業や、エンタープライズ向けの契約をしている企業。 |
| 実践のヒント | 「調子はどうですか?」と聞くだけでなく、「最近リリースされたこの機能は、御社のチームにとって役立つかもしれません」といった価値提供を心がけましょう。 |
92. 活用Tips・ベストプラクティスの配信
| 概要 | ニュースレターやブログを通じて、サービスをより効果的に使うためのヒントやテクニック、先進的な活用事例などを共有する。 |
| メリット | 顧客がサービスからより多くの価値を引き出す手助けとなり、満足度と依存度を高める。 |
| デメリット/注意点 | 顧客がどのように製品を使っているかを深く理解し、役立つコンテンツを作成する能力が必要。 |
| 向いている企業 | 機能が豊富で、ユーザーが全ての能力を把握しきれていない製品。 |
| 実践のヒント | 「パワーユーザー」の顧客を取り上げ、彼らがどのように製品を創造的に使っているかを紹介しましょう。これは企業からの情報よりも説得力があります。 |
93. 顧客満足度調査(NPS)
| 概要 | ネット・プロモーター・スコア(NPS)のような指標を使い、顧客ロイヤルティや満足度を定期的に測定する。 |
| メリット | 顧客満足度を経時的に追跡するための明確な指標が得られる。サービス改善のための貴重なフィードバックを収集できる。 |
| デメリット/注意点 | 回答率が低くなることがある。スコア自体はただの数字であり、その背後にある質的なフィードバックが重要。 |
| 向いている企業 | 顧客体験を体系的に改善したいすべての企業。 |
| 実践のヒント | 低評価者には問題点を理解するために、高評価者には推薦文や紹介を依頼するためにフォローアップしましょう。 |
94. ユーザーインタビュー
| 概要 | 現在の顧客と1対1で詳細なインタビューを行い、彼らの体験、課題、満たされていないニーズを理解する。 |
| メリット | 調査では得られない深い洞察を発見できる。新機能開発やサービス改善に役立つ。 |
| デメリット/注意点 | 時間がかかる。誘導尋問を避けるための熟練したインタビュアーが必要。 |
| 向いている企業 | 製品開発や改良の過程にある企業。 |
| 実践のヒント | 顧客の時間に対する感謝として、ギフトカードなどの小さなインセンティブを提供しましょう。 |
95. ユーザー会の開催
| 概要 | 顧客が集まり、ネットワークを築き、互いに知識や活用法を共有するためのイベント(オンラインまたはオフライン)を主催する。 |
| メリット | コミュニティ意識と帰属意識を育む。ユーザー同士が助け合うことで、サポートコストを削減できる。 |
| デメリット/注意点 | イベントの企画・運営にリソースが必要。 |
| 向いている企業 | アクティブで熱心なユーザーベースを持つサービス。 |
| 実践のヒント | 顧客の一人に成功事例を発表してもらいましょう。ピアツーピアの学習は、これらのイベントで最も価値のある部分です。 |
96. オンラインコミュニティ運営
| 概要 | Slackチャンネル、Discordサーバー、Facebookグループなど、ユーザーが質問したり交流したりするための専用のオンラインスペースを作成する。 |
| メリット | ユーザーが24時間365日互いにサポートし合える、スケーラブルな方法を提供できる。製品フィードバックを集める絶好の場所。 |
| デメリット/注意点 | コミュニティを健全で活発に保つためのモデレーター(コミュニティマネージャー)が必要。 |
| 向いている企業 | 特に開発者向け製品を持つテクノロジー企業。 |
| 実践のヒント | スパムやネガティブな行動を防ぐため、最初から明確なコミュニティガイドラインを設けましょう。 |
97. ファンミーティングの開催
| 概要 | 最も熱心で忠実な顧客(ファン)を招待し、感謝を伝えるための特別なイベントを主催する。 |
| メリット | 最高の顧客との関係を深め、彼らを強力なブランド支持者に変える。 |
| デメリット/注意点 | リソースを要する。参加者の選定は慎重に行う必要がある。 |
| 向いている企業 | 強力なブランドと情熱的なユーザーベースを持つ企業。 |
| 実践のヒント | これを販売イベントにしないでください。舞台裏を見せたり、CEOとのチャットの機会を設けたりするなど、ユニークな体験を提供することに集中しましょう。 |
98. アップセル・クロスセルの提案
| 概要 | 顧客の利用状況やビジネスの成長に基づき、上位プランへのアップグレード(アップセル)や関連サービスの追加(クロスセル)を積極的に提案する。 |
| メリット | 既存顧客からの収益を増加させる。これは新規顧客獲得よりも費用対効果が高い。 |
| デメリット/注意点 | タイミングが悪かったり、押しつけがましかったりすると、顧客関係を損なう可能性がある。 |
| 向いている企業 | 段階的な料金モデルや、一連の関連製品を持つ企業。 |
| 実践のヒント | 提案は、自社がより多くのお金を得るための方法としてではなく、顧客の進化するニーズに対する解決策として位置づけるべきです。データを活用して推奨を正当化しましょう。 |
99. 顧客紹介プログラムの導入
| 概要 | 新規顧客を紹介してくれた既存顧客に報酬を与える公式なシステムを作成する。 |
| メリット | 最も強力なマーケティング資産である「満足した顧客」を活用できる。紹介によるリードは非常に高いコンバージョン率を持つ。 |
| デメリット/注意点 | 報酬体系は魅力的でありながら持続可能でなければならない。紹介の追跡は複雑になることがある。 |
| 向いている企業 | 顧客満足度が高い企業。 |
| 実践のヒント | 「友人に20%割引をプレゼントし、友人が契約したらあなたに5000円のクレジットを」といった両面的なインセンティブを提供すると、参加率が最大化します。 |
100. 契約更新のフォロー
| 概要 | 契約更新日を追跡し、スムーズな更新を確実にするために、事前に顧客に積極的に連絡を取るプロセスを確立する。 |
| メリット | 管理上の見落としによる意図しない解約を防ぐ。過去1年間に提供した価値を再確認する機会となる。 |
| デメリット/注意点 | 日付を効果的に追跡するためにCRMなどのシステムが必要。 |
| 向いている企業 | 年間または複数年契約を持つ企業。 |
| 実践のヒント | ただ請求書を送るだけでなく、「更新レビュー」ミーティングを設け、成功を振り返り、来年の計画について話し合いましょう。 |
101. アップグレードキャンペーン
| 概要 | 上位プランにアップグレードする既存顧客向けに、割引や特別ボーナスを提供する期間限定のキャンペーンを実施する。 |
| メリット | 緊急性を生み出し、短期間でかなりのアップセル収益を上げることができる。 |
| デメリット/注意点 | 頻繁に実施すると、サービスの価値を下げ、顧客が割引を待つように仕向けてしまう。 |
| 向いている企業 | ユーザーをレガシープランから移行させたい企業や、四半期収益を押し上げたい企業。 |
| 実践のヒント | 現在のプランの限界に達している顧客をターゲットにすると、彼らはアップグレードに最も価値を見出すでしょう。 |
102. 成功事例の共創
| 概要 | 単なるケーススタディを超え、顧客と協力して詳細な成功事例を作成し、共同プレスリリースやウェビナー、イベントを通じて宣伝する。 |
| メリット | 最も本物で強力なマーケティング形式。特集された顧客とのパートナーシップを強化する。 |
| デメリット/注意点 | 自社と顧客の双方から、かなりの時間とリソースの投資が必要。 |
| 向いている企業 | 主要なクライアントと強力で長期的な関係を築いている企業。 |
| 実践のヒント | 顧客をプロセスの真のパートナーとして扱いましょう。すべての資料について最終承認を得て、彼らを良く見せることに集中してください。 |
自社に合った施策を選ぶための3つのポイント

BtoBマーケティングの施策は多様であり、どれから手をつけるべきか迷うかもしれません。最適な施策を選ぶには、以下の3つのポイントを意識しましょう。
ポイント1: 顧客と自社の強みを深く理解する
顧客(ペルソナ)はどこで情報を集めているか?
あなたの顧客は、Google検索、業界ニュースサイト、SNS、展示会など、どのチャネルを信頼し、利用しているでしょうか。顧客がいる場所に、あなたのメッセージを届けるのが基本です。
自社の強みを最も伝えられる方法は何か?
あなたの製品・サービスの強みが「視覚的な分かりやすさ」なら動画やデモが、「専門的なノウハウ」ならブログやセミナーが有効です。自社の強みと施策の相性を見極めましょう。
ポイント2: 予算とリソースを考慮する
施策には、コストがかかるもの(広告、展示会出展など)と、時間や手間(人的リソース)がかかるもの(ブログ執筆、SNS運用など)があります。
自社の予算と人員で無理なく継続できる施策を選びましょう。特にコンテンツ制作のような施策は、短期的な成果が出にくいため、継続できる体制がなければ始めるべきではありません。
ポイント3: 短期的な成果と長期的な資産構築のバランスをとる
短期的な成果を求めるなら
リスティング広告や比較サイトへの出稿など、すぐにリード獲得に繋がりやすい施策が向いています。
長期的な資産を築きたいなら
SEOやオウンドメディア、SNSアカウントの育成など、時間をかけて信頼と認知を積み上げていく施策が重要です。
この両方をバランス良く組み合わせ、短期的な成果で事業を回しながら、長期的な資産を育てていく視点が不可欠です。
【より実践的な知識】BtoBマーケティングで成果を最大化するために

102の施策リストと、その選び方を理解した上で、さらに成果を最大化するための「戦略」「組織」「トレンド」という3つの視点について解説します。
7-1. 成果を出すための戦略の立て方(ステップ・バイ・ステップ)
効果的な施策は、優れた戦略から生まれます。以下の4つのステップで、自社のマーケティング戦略を具体化しましょう。
ステップ1:市場環境と自社の立ち位置を分析する(3C分析)
以下の3つの視点から、自社が戦うべき市場と、成功するための鍵(KSF)を見つけ出します。
- 顧客 (Customer): 市場規模や成長性、顧客のニーズは何か?
- 競合 (Competitor): 競合は誰で、どのような強み・弱みを持っているか?
- 自社 (Company): 自社の強み・弱みは何か?
ステップ2:理想の顧客像を定義する(ペルソナ設定)
「どのような企業の、どの部署の、どんな役職の、どんな課題を抱えた人」にサービスを届けたいのかを、一人の人物像として具体的に描き出します。年齢、性格、情報収集の方法まで細かく設定することで、メッセージやコンテンツの方向性がブレなくなります。
ステップ3:顧客の購買プロセスを可視化する(カスタマージャーニーマップ)
設定したペルソナが、自社の商品を認知し、興味を持ち、比較検討を経て、最終的に購入・契約するまでの「旅(ジャーニー)」を、思考や感情、行動、接点といった観点から時系列で可視化します。これにより、「どのタイミングで、どのチャネルで、どのような情報を提供すべきか」が明確になります。
ステップ4:目標と評価指標を定める(KPI設定)
最終的なゴールであるKGI(例:年間受注件数120件)を達成するために、各プロセスで追いかけるべき中間指標であるKPI(例:月間リード獲得数100件、商談化率20%)を具体的に設定します。数値で目標を管理することで、施策の効果測定と改善が初めて可能になります。
7-2. 成果を出すための組織体制と営業連携
BtoBマーケティングは、マーケティング部門だけで完結するものではありません。特に、顧客と直接対話する営業部門との連携は、成果を出すための生命線です。
マーケティング部門の役割
マーケティング部門は、単にリードを獲得するだけでなく、そのリードの質を高め(リードナーチャリング)、購買意欲が高まった段階で営業部門に引き渡す責任を持ちます。
SLA(Service Level Agreement)の重要性
マーケティングと営業の間で、「どのような状態のリードを」「月に何件」「いつまでに引き渡すか」といった共通のルール(SLA)を文書で定めましょう。これにより、「質の低いリードばかりだ(営業)」「渡したリードをフォローしてくれない(マーケ)」といった部門間の対立を防ぎます。
定期的な情報共有
週次や月次で定例会を開き、KPIの進捗、うまくいっている施策、顧客からのフィードバックなどを共有する場を設けましょう。この情報交換が、戦略や施策の精度を高めます。
7-3. 2025年のBtoBマーケティング最新トレンド
最後に、今後BtoBマーケティングで重要性が増すであろう3つのトレンドをご紹介します。
トレンド1:生成AIの活用
ブログ記事やメール文面の草案作成、市場調査データの要約、広告クリエイティブのアイデア出しなど、AIを「優秀なアシスタント」として活用することで、マーケターはより戦略的な業務に集中できるようになります。
トレンド2:Cookieレス時代への対応と「一次情報」の価値向上
サードパーティCookieの規制強化により、リターゲティング広告などの従来の手法が難しくなります。その結果、自社で収集した顧客データ(ファーストパーティデータ)や、独自の調査・事例といった、他では手に入らない「一次情報」の価値が飛躍的に高まります。ホワイトペーパーやウェビナーによるリード獲得の重要性は、ますます増していくでしょう。
トレンド3:ABM(アカウントベースドマーケティング)の進化
不特定多数にアプローチするのではなく、自社にとって最も価値の高い優良顧客企業(ターゲットアカウント)を特定し、その企業に合わせてマーケティングと営業が一体となってアプローチする「ABM」がさらに進化します。AIによるターゲットアカウントの選定や、個別コンテンツの自動生成などが可能になり、よりパーソナライズされたアプローチが実現します。
BtoBマーケティングでよくある失敗と対策
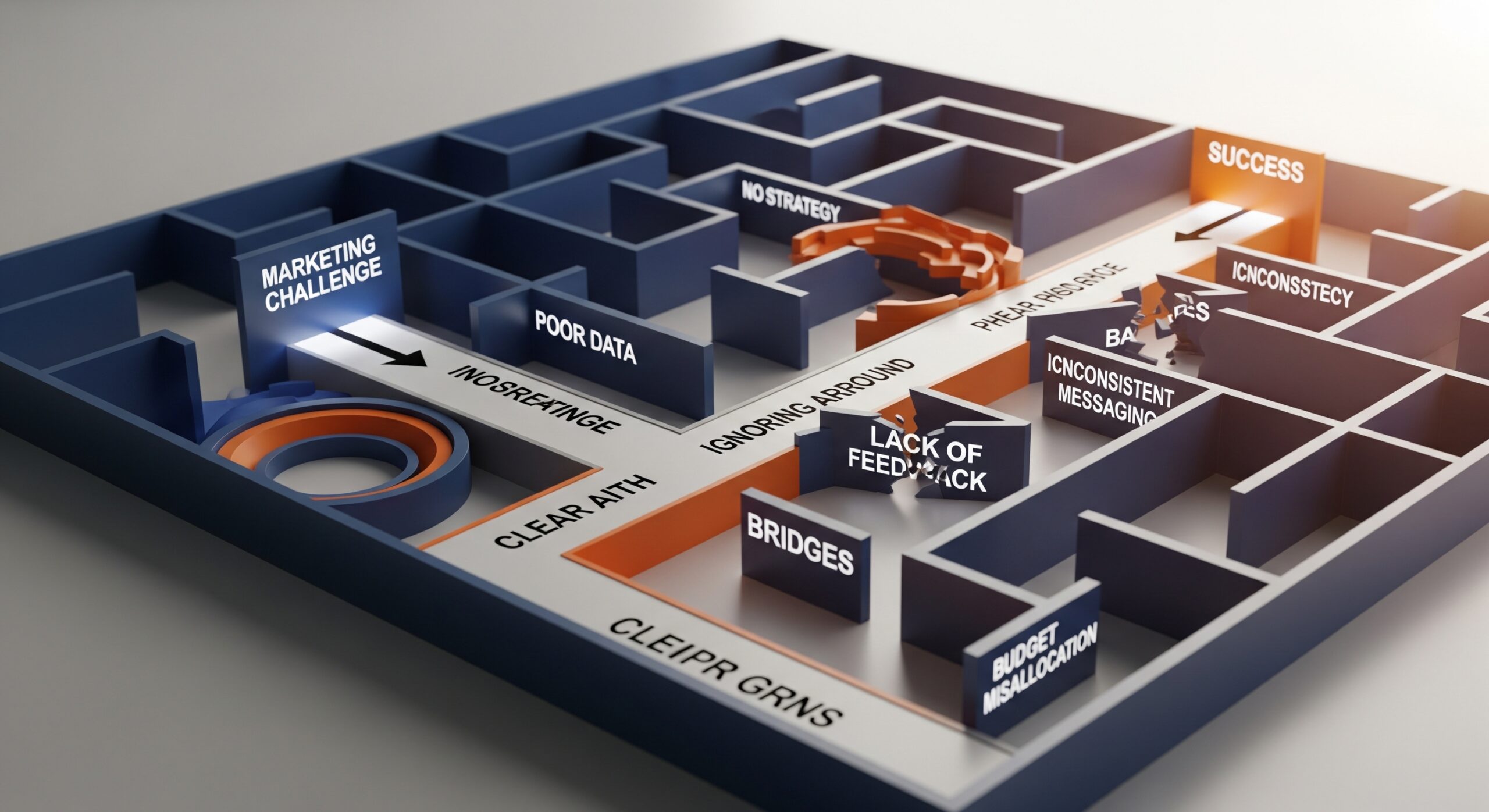
失敗例1:戦略なき施策の乱発
状況: 「SEOが良いらしい」「ウェビナーが流行っている」といった断片的な情報に飛びつき、目的やターゲットが曖昧なまま施策を始めてしまう。
対策: 「誰に、何を伝え、どうなってもらいたいのか」という戦略の根幹をまず固めましょう。戦略があれば、数ある施策の中からでも、自ずとやるべきことは絞られます。
失敗例2:営業部門との連携不足
状況: マーケティング部門は「リードを渡しているのに営業がフォローしてくれない」、営業部門は「質の低いリードばかりだ」とお互いに不満を持っている。
対策: リードの定義(どのような状態になったら営業に渡すか)や、部門間の役割分担を明確に定めるSLA(Service Level Agreement)を締結しましょう。定期的な情報交換の場も不可欠です。
失敗例3:短期的なROIに固執しすぎる
状況: コンテンツマーケティングやSNS運用など、成果が出るまでに時間がかかる施策を「すぐに売上に繋がらない」という理由で途中でやめてしまう。
対策: 施策の特性を理解し、KPIを適切に設定することが重要です。例えば、コンテンツマーケティングの初期段階では、売上ではなくPV数や検索順位をKPIとし、施策の健全性を評価します。
まとめ:小さな成功を積み重ね、BtoBマーケティングを会社の文化に

本記事では、BtoBマーケティングの施策を102個、網羅的に解説しました。しかし、最も重要なのは、これらすべてを実行することではありません。
自社の顧客を深く理解し、戦略的な視点を持って、自社に合った施策を一つでもいいから試してみること。そして、その結果をデータで振り返り、改善を繰り返すこと。
この地道なPDCAサイクルを回し、小さな成功体験を積み重ねていくことが、最終的に大きな成果へと繋がります。この記事が、貴社にとってその確かな一歩を踏み出すための羅針盤となれば、これほど嬉しいことはありません。